歯周病の本当の原因は細菌じゃない!? 歯を溶かす“免疫の暴走”とは?
2025/05/20

こんにちは。東京(外苑前)の自由診療専門歯科医院、サウラデンタルクリニック青山です。
歯磨きのときに「歯ぐきから血が出る」「腫れている」「なんとなくグラグラする」——こんな症状がある方はいませんか?
それ、もしかすると“体が自分の歯を攻撃している”サインかもしれません。
歯周病は「歯の周囲にいる細菌のせいで歯ぐきが腫れる病気」と思われがちですが、実はそうではありません。
本当の犯人は“あなたの免疫反応”にあります。
この記事では、歯周病の本当のメカニズムと、なぜ体が自分の歯を壊してしまうのかを、専門的かつわかりやすく解説します。
【第1章】歯周病は「細菌による感染症」…だけど、破壊するのは“自分自身”?
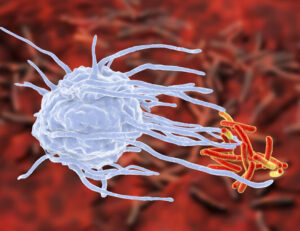
歯周病は、歯の周囲にいる細菌による感染症です。
歯のまわりにたまったプラーク(歯垢)の中で増殖した歯周病菌が出す「内毒素(LPS)」が原因で、炎症が起こります。
でもここで重要なのは、「歯周病菌が歯ぐきを直接壊すわけではない」という点です。
細菌が出す毒素を感知すると、私たちの体は「これは危険だ!」と判断し、白血球を中心とする免疫細胞を大量に送り込みます。
白血球は、毒素を分解・除去しようと活性酸素や酵素を放出しますが、この過程で健康な歯肉の細胞やコラーゲン繊維も巻き添えにして壊してしまうのです。
つまり、歯周病によって歯ぐきや骨が壊れるメカニズムは、「細菌 vs 体の免疫」という“戦場”が口の中に生まれているということなのです。
ポイント!歯周病の正体は“あなたの身体の反応”だった
歯周病=細菌の感染症というのは半分正解で、半分不正解。
実際には「細菌が出す毒素(内毒素:LPS)」に対して免疫細胞(白血球など)が過剰反応。
白血球が毒素を攻撃する際に、自らの組織(歯ぐきや骨)まで壊してしまう。
この自己破壊的な反応が、歯肉の腫れや歯を支える骨の喪失を引き起こす。
【第2章】なぜ骨まで溶ける?「歯を失うリスク」と体の自己防御の関係

歯ぐきの炎症が長期間続くと、今度は“歯を支える骨”にまで影響が及びます。
人間の体は、「この歯のまわりは毒素で汚染されている」と判断すると、自ら骨を溶かして“問題の歯を排除しよう”とします。
これを担うのが「破骨細胞(はこつさいぼう)」という骨を分解する細胞です。
これは、毒素による全身への影響を防ぐための防御反応ともいえますが、結果的に「歯を支える骨が溶ける=歯がグラグラになる」という大きなリスクを引き起こします。
歯周病が“沈黙の病”と呼ばれる理由はここにあります。 多くの人が痛みを感じることなく進行し、気づいたときには「歯が抜けそう」「すでに抜けてしまった」という事態になってしまうのです。
【第3章】人によって進行スピードが違うのはなぜ?——リスク因子とは
歯周病は、すべての人が同じように進行するわけではありません。
同じように歯磨きをしているのに「ある人は歯ぐきが健康、別の人はどんどん悪化する」ということが起きるのはなぜでしょうか?
それには「リスク因子(リスクファクター)」が関係しています。
現在までに知られている代表的なリスク因子は以下の通りです。
加齢(40代以降)
喫煙習慣
糖尿病
肥満
ストレス
妊娠やピルの長期服用(女性)
遺伝的要因(家族に歯周病で歯を失った人が多い)
特に喫煙と糖尿病は、歯周病の“二大悪化因子”と呼ばれるほど危険性が高いものです。
当院では、初診時に生活習慣や既往歴についても詳しく伺い、一人ひとりのリスクに応じた予防・治療計画をご提案しています。
【第4章】なぜ「歯石がないのに歯周病」になる?見えない敵との戦い
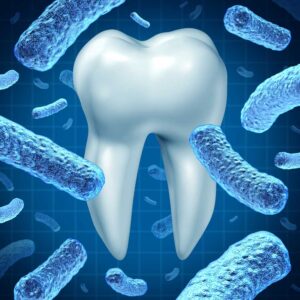
「歯石を取ったのに歯ぐきが腫れている」「目に見える汚れはないのに歯周病が治らない」
そんな声をよく耳にします。
その理由は、歯周病菌の“餌”が人間の食べ物ではないからです。
むし歯菌は糖を栄養にしますが、歯周病菌はそうではありません。
ポケット内に剥がれ落ちた上皮や血液、唾液中のタンパク質などを餌に、食事をしていなくてもどんどん増殖します。
つまり「食べてない=菌が減る」わけではなく、「常に菌と戦っている状態」が続くのです。
さらに、歯石やプラークが目に見えなくても、バイオフィルムという膜状の細菌群が根の深部にへばりついていることもあり、肉眼では確認できない“隠れ汚れ”も要注意です。
【第5章】治療の第一歩は「炎症を静めること」。急いで歯石を取るのはNG!
歯周病治療で多くの方が勘違いしているのが、「とにかく歯石を取れば治る」という考え方です。
実は、強い炎症がある状態で無理に深い歯石を取ろうとすると、かえって歯ぐきを傷つけ、炎症を悪化させる可能性があります。
まずは、ブラッシングと表面清掃で炎症を抑えることが先決です。
サウラデンタルクリニック青山では、歯周病の初期治療として、スウェーデン・イエテボリ大学の歯周病治療法に基づいた“体にやさしいアプローチ”を実践しています。
患部に白血球が過剰反応しないよう、段階的にポケット内の環境を整える
目に見えないバイオフィルムを除去するためのマイクロスケーリング
専門的なブラッシング指導による自己ケアの確立
このように、ただ機械的に「歯石を削る」のではなく、「体の反応を鎮める」ための戦略的なアプローチが不可欠なのです。
【第6章】1日1回の“正しいブラッシング”が最大の治療

歯周病は「病院で治す」ものではなく、「自宅で守る」病気です。
歯ぐきの炎症が起き始めるのは、プラークがついてから約72時間後。
つまり、理論上は3日に1回すべての汚れを完璧に落とせば予防できることになります。
しかし、実際には100%プラークを除去することは不可能です。
そのため、1日1回、時間をかけてていねいに歯磨きをすることが最も効果的なのです。
また、ブラッシングには「マッサージ効果」もあります。
歯ぐきをやさしく刺激することで血行が促進され、炎症物質や老廃物が流れやすくなり、免疫力も上がります。
当院では、患者さまの口腔内の状態や癖に応じて、オーダーメイドでブラッシング指導を行っています。
ポイント!治療が“うまくいかない人”に共通する3つの落とし穴
歯石だけ取っても再発するケースが多い
口の中に住む300種類以上の細菌を完全にゼロにするのは不可能
重要なのは「古い細菌を溜めない=日々の丁寧なブラッシング」
【まとめ】歯周病は“免疫との共存”がカギ。体に優しい治療で守る未来の歯
歯周病は「細菌との戦い」ではなく、「免疫との共存」の病気です。
サウラデンタルクリニック青山では、単なる歯石除去ではなく、歯ぐきと免疫のバランスを整える「身体にやさしい歯周病治療」を提供しています。
マイクロスコープ(歯科用顕微鏡)による精密な歯周ポケット検査と処置
目に見えない細菌まで丁寧に除去します。
歯周再生療法にも対応(条件あり)
失った骨の回復を目指す先進的な治療も行っています。
金属を使わない審美的な補綴(セラミックなど)で見た目と機能の両立
歯周病後の被せ物も長期的な健康を考慮して設計します。
管理型予防(メンテナンス)による再発防止
1人あたりの時間をしっかり確保し、じっくり診させていただきます。
当院からのメッセージ

歯周病は「自分の体が、自分の歯を壊してしまう病気」です。
でも裏を返せば、「自分の体が、自分の歯を守る力を持っている」ということでもあります。
当院では、治療だけでなく“予防”と“教育”を通じて、患者さまが自分の歯と一生付き合っていけるようサポートしています。
「歯を抜かずに守りたい」
「根本的に治したい」
「もう、治療を繰り返したくない」
そう思ったときが、人生の歯科治療の転機です。
サウラデンタルクリニック青山 :https://www.hori-dental.com/
〒107-0061 東京都港区北青山2-7-25 神宮外苑ビル8階
電話:03-3405-6480
交通アクセス
電車でお越しの方:
東京メトロ銀座線「外苑前駅」2b出口徒歩1分


